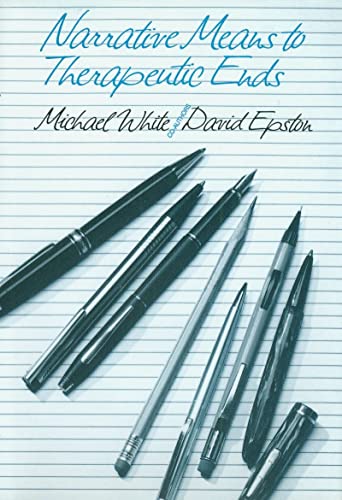0)はじめに
1年ほど前、このブログを「ケア」に関する読書の記録に使いたいという記事を書いた。しかし結局その読書記録は2本記事を書いただけで止まってしまっていた。今回はそれを久々にやってみようということで、『ピア・サポートの社会学』という2013年に出版された本を取り上げ、まとめと考察を行いたい。
概要を述べておくならば、タイトルの通り、この本は「ピア・サポート」を取り扱った本である。
ピア・サポートとは福祉用語で、医者のような専門家によるサポートと対比して、共通した病いや障害、苦しみなどを抱えた仲間(ピア)同士が互いに支援し合う活動のことを意味する。代表的なものにはセルフヘルプ・グループ(自助グループ)とよばれる活動があり、例えばアルコール依存症に苦しむ当事者たちが集まって自らの体験を共有し合うためのグループなど、無数のセルフヘルプ・グループが世の中には存在している。
本書は、こうしたピア・サポートがどのような働きを持っているのか,またどのようにあるべきなのかを明らかにすることを目的に,伊藤智樹ら5人の研究者の共著として執筆された。
そんな本書の大きな特徴は、ピア・サポートを分析するための道具として、「ナラティヴ・アプローチ」を用いている点にある。簡単に言っておけば、ナラティヴ・アプローチとは、人の精神的な苦しみやそこからの立ち直りに「物語(ナラティヴ)」が深く関わっているとみなす考え方のことだ。
ピア・サポートは、制度やライフハックに関する情報交換の場と見ることもできる。しかし本書が描き出そうとするのは、誰かが自らの経験を物語り、他者がそれを聴く場としてのピア・サポートの姿である。ピア・サポートの場が苦しみを抱えた人を支えることができるのはなぜか。それは、そこにある〈語る-聴く〉関係が、ある特定の性格を備えた〈語る-聴く〉関係だからにほかならない。
そしてそんな叙述を通して、本書は読者に深く問いかけてくる。良き聴き手であるとはどういうことであろうか、と。
本記事では、最初にナラティヴ・アプローチについて簡単に確認したうえで、本書の趣旨を第1章と第2章、および第4章を中心にまとめる。その後、私の感想と考察を述べていくこととしたい。
* * *
1)ナラティヴ・アプローチとは
本書の内容を見る前に、ナラティヴ・アプローチについて、本書以外の説明も参考にしながら軽く確認しておきたい。
ナラティヴ・アプローチは、1990年頃より形作られてきた、ケアの領域における方法論の一つである。その根底には、社会構成主義という社会学理論に由来する、ある考え方がある。それは、現実というものは私たちの語りや認識から独立してあるのではなく、むしろ私たちは出来事を「物語(ナラティヴ)」*1という形に落とし込むことによって、現実を主観的に作り上げている、というものだ。
ちなみにここでいう「物語」とは、小説や映画といったフィクションのことではない。ナラティヴ・アプローチの日本における第一人者である野口裕二は次のように説明する。
ナラティヴは、複数の出来事を時間軸上に配列することで成り立つひとつの言語形式である。
(野口裕二『ナラティヴと共同性』p53)
野口が言うように、ここでいう「物語」とは、私たちが出来事(現実の出来事か虚構の出来事かにかかわらず)を時間的な連なりのもとで語ったり理解したりするために用いる一般的な言語形式のことである。なお本書『ピア・サポートの社会学』では、物語は、〈「事象」の連鎖〉として定義されている(本書p12)が、これも上の定義とおおむね共通するものである*2。
物語は、私たちの経験する個々の出来事に文脈を与え、出来事の「意味」を作り出す。そしてまた、その出来事の先にある未来についてのイメージを私たちにもたらす。
ナラティヴ・アプローチにおいて問題となるのは、特に、自己物語(セルフ・ナラティヴ)と呼ばれる、私たちが自分自身について理解する際の物語である。
私たちは、自分にまつわる過去の重要な出来事や現在の出来事を物語の形につなげて語ることで、自身が何者であるかを解釈し、未来についてのイメージを作り上げている。そしてナラティヴ・アプローチは、人の精神的な苦しみの背後には、自らの体験や感情がうまく位置づく自己物語を見出せていない状況があるとみる*3。
重要なのは、その自己物語のあり方は、当人が自分の意志で自由に決められるわけではないということである。
というのも、自己物語は、「人はこう生きるべきだ」といった社会に浸透した価値観や、他者の語る物語の影響下で形作られているからである。では、どのようにすればその物語は変容することができるのだろうか。まさにこれが、ナラティヴ・アプローチに基づくケアが取り組んでいく課題となる*4。とはいえ、ここでそのケアの技法(ナラティヴ・セラピー)に具体的に立ち入ることは避け、そろそろ本書『ピア・サポートの社会学』の内容に入っていこう。
* * *
2)本書のまとめ
さて、本書を牽引する問いは、ピア・サポートは人の苦しみに対してどのように働くのか、というものである。まさにこのピア・サポートの「どのように」を分析するための手立てが、ナラティヴ・アプローチとなる。
〔本書の〕どの執筆者も、苦しみの中にあって仲間と会うことに何らかの意味があると考えている点では一致しています。問題なのは、それがどのような点で「意味がある」といえるのかであり、そのことに関して少なくとも私たち自身が心の底から納得できるような論理的な説明に、「物語」という観点を導きとして、挑んでみたいのです。
(本書 iv、〔〕内は本記事筆者による補足)
本書は、ピア・サポートに参加する人々へのインタビューを通してピア・サポートを分析していく。そして上の問いのもとで本書が描き出すのは、ピア・サポートの「人々が物語を通して互いを触発し影響を与えるプロセス」(本書p29)としての姿である。ここではそのアウトラインを2つの方向から確認しよう。
1.共同体の物語
まず鍵となるのは、自己物語に加えて、「共同体の物語(コミュニティ・ナラティヴ)」というもう一つの概念である。共同体の物語とは、ある共同体のメンバーそれぞれの語る自己物語が持つ,一定の共通した筋や語り口のことを指す(本書p21)。この共同体の物語という概念が、ピア・サポートにおいて共通した苦しみを持つ他者と出会うことの意味を説明してくれるものとなる。
例えば本書の第2章では、認知症になった家族を介護する人たちのセルフヘルプ・グループ(認知症家族会)における共同体の物語が紹介される。本書はそれを「手抜き介護の物語」と名付ける。
社会、つまり認知症家族会の外には、認知症患者に寄り添い心を込めて介護をすることを良しとする「献身的介護」という規範がある。それは立派なものでありながらも、しばしば介護する側の家族を縛り付けるものとなり、場合によっては家族を精神的に追い込んでいくものにもなりうる。それに対し、このセルフヘルプ・グループの中では、メンバーたちによって、家族が自分を追い込まないように適度に手を抜きながら介護をすることが肯定的に語られる(本書p47)。これが「手抜き介護の物語」である。認知症の家族を介護する中で持つことになる独特な経験や複雑な感情は、献身的介護の物語のもとでは語りづらい。手抜き介護の物語はそれを語りやすくし、そこから、介護とどう付き合っていくかというその人自身のあり方が見出されていくわけである。
このように、共同体の物語は、しばしば社会一般に浸透した価値観とは別様な価値観を示す。ピア・サポートの場に参加した人は、他者の語りを通して提示されるこの共同体の物語に触発されることで、それまでの自己物語を支配していた価値観から自由になった、新たな物語の筋を見つけられるようになるのである。
こうして、ピア・サポートの場で出会う他者は、社会の一般的通念のもとでは語れない物語を語ることを促し、その語りを聞き届ける存在として理解することができる。そうした他者との交流の中で獲得する新たな自己物語が、苦しみの中にあった人に生きる方向性を教え、生き抜く力を与えるのである。ここにピア・サポートの意義があるというのが、本書の最も基本となる考え方である。
2.ピア間の経験の異質性
ただし、本書が同時に強調するのは、物語を通したこのような肯定的な変化は、ピアが集まる場において決して自動的に起こるものではないということである。はじめに上記の見通しが語られたのち、各章で語られていくのはむしろこのことであると言ってもよい。
ここではその例として、「葛藤を承認すること、沈黙を共有すること」と題された本書第4章の内容を少し詳しく見ておこう。
① あしなが育英会と自死遺児
第4章では、親を亡くした子どもたちを支援するグループ「あしなが育英会」を舞台に、自死遺児たちの手記集『自殺って言えなかった。』が編まれるにいたるまでの、本人たちの葛藤やグループ全体での試行錯誤が描写される。なお自死遺児とは、親を自死、つまり自殺によって亡くした子どものことである。重要なのは、彼ら彼女らは、交通事故や病気など、まったくどうしようもない要因によって親を亡くした遺児たちとは異なった苦しみを抱えているということである。
手記集に寄せられた自死遺児たちの手記には、共同体の物語と呼べそうな、ある共通した筋がみられるという。
あしなが育英会には「つどい」と呼ばれる合宿形式のイベントがある。あしなが育英会の支援を受ける遺児たちは基本的にそれに参加することになっており、その中で設けられる「自分史語り」の時間に、自らの経験や思いを参加者たちの前で語ることになっている。手記集に見られる共通の筋とは、この「つどい」に参加して暗い葛藤の中にあった気持ちや認識に肯定的な変化が訪れた、というものだという(本書p98)。
さて第4章が焦点を合わせようとするのは、この共通の筋そのものというより、この筋に沿った物語が語られるようになるまでのプロセスである。
共同体の物語だけに目を向けると、それを語れるようになることが参加者の「目標」であるかのように捉えられてしまうおそれがある。しかしそのプロセスを、既成の物語に自死遺児たちが自らを合わせていったという単純なものとして捉えてはならない。そこには、自死遺児たちが語りを行いやすくなるようにするための、あしなが育英会内部でのさまざまな工夫があったのであり、そうした工夫の積み重ねを見過ごすとピア・サポートを誤って理解してしまうことになる。
② 自死遺児ミーティングとパスルール
問題は、経験の共通性を拠り所にして集まったセルフヘルプ・グループの中で、いかにしてメンバー間の経験の異質性を見過ごさないようにするか、というところにある。
第4章では、インタビューをもとに、あしなが育英会の中で行われてきた異質性を承認するための2つの試みが紹介される。その1つは「つどい」とは別に設けられた「自死遺児ミーティング」であり、もう1つは「つどい」の内部での自分史語りに関するルール作りである。
「自死遺児ミーティング」は、あしなが育英会の支援を受ける学生が等しく参加する「つどい」と異なり、名前の通り、自死遺児だけが参加するクローズドなミーティングである。
あしなが育英会は、交通事故によって親を亡くした子どもたちのための団体として出発し、そこから病気や自死によって親を亡くした子どもをも支援するように展開していった(本書p96)。そんなあしなが育英会の「つどい」の中に、自死遺児たちの居場所は、初めから確保されていたわけではなかったという。交通事故と自殺とでは、完全に受動的な死かいわば自ら選んだ死かという意味で、死因の質が異なる。自死遺児支援が始まる前の遺児たちによる会議では、自死という死因を正面に出すことで募金の金額が減ってしまうのではないかという意見が出たことすらあったそうだ(本書p109)。
自死遺児ミーティングは、そんな当初の団体内の雰囲気の中で、自死遺児たちを居づらさから守るために始められた。そして自死遺児たちは、一方では自死遺児ミーティングの中で自らの思いと向き合い、他方ではそれを「つどい」で語りに乗せることで、少しずつ自分たちの言葉を手に入れ、団体の中での居場所を作っていったのである。
それ〔=『自殺って言えなかった。』の中で語られていること〕は、既成の「共同体の物語」に自己物語を合わせていくというプロセスではなく、むしろ1人ひとりの遺児たちが自分自身のなかで内省し、またそれを「つどい」のなかで、必ずしも自死遺児ではない人も含まれる聞き手の前で語る行為を経て言葉に定着させていったものだと考えられるのです。
(本書p111)
こうした「つどい」の外部での試みとともに、「つどい」の内部でも、親を亡くした子供たちの経験の異質性を汲み取るためのしくみが模索されていった。そうしてできたのが、自分史語りにおける「パスルール」である。
先述のように「つどい」の中心は参加者1人ひとりが順番に自分史を語る時間にあるわけだが、パスルールとは、そこで「語らない」(=パス)という選択をしてもよいということを明示化したものである。たとえ共通の経験を持った仲間の語りが連ねられていく空間であっても、語れることは当たり前のことではない。ある人の中には、そこにいる他者と同じような形で経験を語ることを阻むような、言葉にならない葛藤があるかもしれない。パスルールには、単に話さないことを許すというだけでなく、まさにそうした語れなさそのもの、語れない状況を承認するという機能がある(本書p114)。
交通事故や災害、病気などによって死別した遺児とは異なる葛藤を抱える自死遺児たちを受け入れるために、このパスルールは不可欠なものだったという。パスルールは、「つどい」の中で、明示的に語られた物語だけでなく、葛藤の中にある見えない物語までもが居場所を持つことを可能にし、それによって、言葉にならない葛藤を抱えた当人が彼/彼女なりの仕方で主体的に「つどい」に参加することを可能にしていったのである。
③ 物語の共同体としてのあしなが育英会
このように、あしなが育英会の中では、親を亡くしたという経験の共通性の中にある異質性を大切にするための試行錯誤が、真摯に積み重ねられてきた。手記集『自殺って言えなかった。』に見られる共同体の物語は、参加者が自らをそこに一致させるべきものとしてあらかじめあったのではなく、上記のような模索のプロセスの中で行ったり来たりを繰り返しながら、あくまで結果として生まれていったのだと見なければならない。
以上を踏まえ、本章は最後に、セルフヘルプ・グループとしてのあしなが育英会の姿を改めて捉え直す。それは、既成の「共同体の物語」を共有するための場というよりも、互いに影響を与えながら自己物語を語っていくためのつながりをつくる場であり、そうした語りのプロセスをともに歩む場なのである。本章は、このような意味であしなが育英会を「物語の共同体」であると言う。
重要なのは、その語りのプロセスに含まれるのは明示的な語りだけでなくてもいいということだ。パスルールが象徴するように、そこには葛藤や沈黙が含まれていてもいい。葛藤や沈黙も立派なメッセージなのであり、葛藤や沈黙にただ居合わせるということも、聴き手としての立派なあり方なのである。本章は、次のような言葉で結ばれる。
そのような場・過程が生を支えてくれるのは、必ずしも「共同体の物語」を語れるようになることのみによってではありません。葛藤を承認すること、沈黙を共有すること、これらのことにもよっているのです。
(本書p119)
ピア・サポートは、一つの共同体の物語によって同質性を強要する場であってはならない。むしろ、そうしてしまうことの危険性に敏感であろうとする姿勢こそが、ピア・サポートを真に豊かな力を持ったものにする。この第4章はそんな洞察を提示している。
この他にも本書の各章では、ピア・サポートの具体的な現場に目を向けながら、グループの中でも個々人によって経験は多様であるということ、また、同じ共同体の物語を語れるようになることを目標のように捉えてしまうと個人に対する圧力になりかねないということが、形を変えて繰り返し語られている。ピア・サポートの場をナラティヴ・アプローチによって理解できるような肯定的な変化の場にするためには、このような危険性に敏感になり、自身の経験を参加者それぞれが安心して語れるようにするための工夫をすることが必要なのである。
* * *
3)考察と感想:「聴き手」であることについて
ここからは、私の考察や感想を述べていきたい。
この本の魅力の根底にあるものは、「聴く」ということに関するある信念であるように思う。聴くとは何であろうか。良き聴き手であるとはどういうことであろうか。そう問われたならば、著者たちはこう答えるのではないか。
良き聴き手であるとは、別様な(オルタナティヴな)語りの可能性に敏感であるということ、そしてそのために、未だ語られていないものに常に耳を澄ますということだ、と。
このことを浮き上がらせるために、ピア・サポートに関する本書の分析を整理し直してみよう。足がかりとなるのはやはり、本書のキーワードである「共同体の物語」である。
1.別様な物語としての共同体の物語
まず「共同体の物語」のポジティヴな側面について考えてみよう。
既に見たように共同体の物語とはメンバー間で共有された一定の語り筋や語り口のことであるが、セルフヘルプ・グループの共同体の物語は無条件にポジティヴな働きをするわけではなく、両面的な性格を持っている。
例えば「献身的介護の物語」に対置される「手抜き介護の物語」のように、一方では共同体の物語は、社会に浸透した支配的な(ドミナントな)物語のもとで苦しんでいたり、苦しみの中で物語を見いだせなくなっていたりする人にとって、自らを生きやすくするための物語を見出す拠り所になる。他方で、共同体の物語は、場合によってはそれ自体が「正しい物語」としてセルフヘルプ・グループの参加者たちの語りを縛ることで、息苦しさをもたらすものにもなりうる。
共同体の物語がポジティヴな働きをする時、それは、共同体の物語が自己物語の「正しい」語り方を教えるからではなく、共同体の物語が支配的な物語を相対化し、別様な語り方があっていいんだという「可能性」を教えてくれるからなのだと理解しなくてはならない。
なお、共同体の物語の持つ働きは、参加者たちに共有されたある姿勢に由来するものと言うこともできるだろう。
というのも、共同体の物語が存在しているのは、参加者個々人の語りの中だからだ。参加者たちはみな、共通した支配的な物語のもとで苦しんだ経験を持っており、なんとかその物語から自由になろうとした経験を持っている。それゆえに参加者たちは、語り手として、聴き手として、その支配的な物語とは別様な語りの可能性を大切にすることができる。共同体の物語の機能は、まさに参加者たちのこうした姿勢が作り出す空気によって生み出されるものであるのかもしれない。
さて、こうして共同体の物語の概念を注意深くとらえるならば、共同体の物語によって描出されるピア・サポートの働きの中心は、〈別様な語りの可能性を覆い隠すものからの解放〉という点にあると言えるのではないだろうか。
例えば、認知症になった親へのネガティブな感情のように、社会に浸透した支配的な物語のもとでは否定的にしか語れなかったり存在感を与えてもらえなかったりする経験や感情も、それを言葉にして認めることができれば、そこから出発する肯定的な物語を描くことができるかもしれない。しかし、そうしたいわば〈自己物語探し〉ができるためには、支配的な物語に脅かされない空間が無くてはならないのである。
ピア・サポートという仲間との出会いの場は、まさにそうした空間であることができるからこそ、癒しの力を持つのであろう。
2.未だ語られていないものに耳を澄ますこと
共同体の物語のポジティヴな側面を通して浮かび上がったのは、ピア・サポートの外側と内側がどのように異なった空間であるかということである。この文脈における〈別様な語りの可能性を覆い隠すもの〉とは、社会に浸透した支配的な物語のことであった。しかし、〈別様な語りの可能性を覆い隠すもの〉はピア・サポートの外側にのみあるわけではない。
本書であしなが育英会の事例を通して取り出されたものを振り返ろう。それは、グループ内での経験の異質性を大切にし、葛藤や沈黙の中にある言葉にならないものに耳を澄まそうとする姿勢であった。それはまさに、グループの内部に再び〈別様な語りの可能性を覆い隠すもの〉が生まれることを防ぐための姿勢であると言うことができるだろう。
ピア・サポートの内部で別様な語りの可能性が覆い隠されてしまうのは、共同体の物語がそれ自体支配的な物語として固定化された時である。ある人がセルフヘルプ・グループに参加して共同体の物語に触発された語りを行ったとしても、今までうまく語れなかった経験や思いのすべてがその語りの中で居場所を得られるとは限らない。そして、未だ語られていないモヤモヤとした何かが残っていると感じ、それをなんとかして語りの中に掬い上げたいともがくとき、その葛藤の中にこそ、その人の経験の個別性は宿るのである。そんな時、グループ内の多数が語る共同体の物語──例えば喪失からの立ち直りの物語──を、語れるようになるべき正しい物語として固定化してしまったならば、それはその人の経験の個別性を、ひいてはその人の心そのものを暗黙裡に踏みつけにするに等しいだろう。ピア・サポートの場は、仲間が集まっているからといって、必ずしも心が守られる空間になるとは限らない。
必要なのは、共同体の物語を固定化しないことである。共同体の物語がメンバー間で自然と共有された一定の語り筋や語り口である以上、それを否定することはナンセンスだ。しかし、固定化されて抑圧的なものになることを防ぐことはできる。大切なのは、その共同体の物語が取りこぼしてしまうものがあるかもしれないということ、そして、それが語りの中に居場所を得た時、まったく別様な肯定的な物語が立ち現れるかもしれないということ、これらのことを忘却しないことである。
そのためには、グループ全体が葛藤や沈黙を認め、その奥底にある、未だ語られていないものに常に耳を澄まさなくてはならない。その姿勢は、あしなが育英会のようにグループ内のしくみという形で実現されることもあれば、メンバーそれぞれの聴き手としての心がけという形で実現されることもあるだろう。これに関してもやはり、何らかの支配的な物語に苦しんだ経験があるからこそそうする真摯さを持つことができるということもあるかもしれない。いずれにせよ、この姿勢が備わってこそ、ピア・サポートの場は、内側で生じうる暴力性からも自由になった、真に人の心を支えることのできる場となるに違いない。
3.「声」という着眼点
ここで一つ補足的に触れておきたい事柄がある。
それは本書の第1章で探究の準備を行う際に触れられる「声」というものについてである。第1章では、ピア・サポートを物語の観点から分析するための主要な着眼点が6つ挙げられる。そして「声」はその一つである*5。この「声」に関する叙述に注意を向けると、上で「未だ語られていないものに耳を澄ます」として述べたことが本書の一つの核心であることがわかるように思う。
ここでいう「声」とは何か。それは、文字通りの声というより、言いよどみや沈黙のように、語る場面に現れるが語りの内容そのものには含まれないような要素のことを広く意味する。これまで述べてきた葛藤や沈黙の承認ということは、まさしくこの「声」にかかわることとして理解することができる。本文では次のように言われている。少し長いが引用しよう。
このように「声」は、物語を表面的にみたときにしばしば見逃されがちな要素を指します。それは、何らかの断片的な言葉である場合もあるし、沈黙や言い直しといった形をとることもありえます。これらは、物語の中で機能するかどうか未だわからないものです。(……)そのような要素を、私たちはしばしばノイズのように扱って、苦しみの中にある人の物語をわかりやすい形におしこめようとしがちです。しかし、そのようなときこそ、むしろ声に注目して、物語の複層性をとらえることが、苦しみになお耳を傾けることにつながっていきます。(本書p18f)
この「声」を補足的にではなくむしろ主要な着眼点として前に押し出そうとしていることは、本書の際立った点である。
通常、ナラティヴ・アプローチをとる、つまり物語に着目するとは、言語に着目することを意味している。例えば「物語」が通常言語形式の一種として定義されることは本記事のはじめに見た通りであるし、またケアの文脈とは異なるものの、哲学者の野家啓一は『物語の哲学』の中で、「物語る」ことを「言語行為」の一種として定義している(野家啓一『物語の哲学』p16ff)。
しかし「声」は、明示的に特定の何かを表象するわけではないという意味で、非言語的なもの、あるいは言語の周縁にあるものである。本書は、あえてこの非言語的な要素を、主要な着眼点としてはじめから準備しているのである。
これは、著者たちが「声」にこそピア・サポートを探究するための本質的な手がかりがあると考えているからにほかならない。「声」が示すのは未だ物語に組み込まれていないものであり、それが言葉になったときに別様な物語が立ち現れるかもしれないという可能性──物語の複層性──である。であるならばここからは著者たちが、共同体の物語を共有することよりもむしろ、共同体の物語を固定化せずに別様な物語の可能性をかき消さないようにすることに、ピア・サポートの重要なあり方を見出そうとしていることがわかるだろう。この文脈にもとづき、共同体の物語もあくまで支配的な物語からの解放という面に重点を置いて理解する必要がある。
4.別様な語りの可能性をくみ上げる場としてのピア・サポート
そろそろまとめに向かおう。共同体の物語の持つポジティヴな機能の本質は何なのか、共同体の物語がネガティブに機能することを防ぐためには何が必要なのか、これらの観点からここまで述べたように本書の内容を振り返ってみた時、本書がピア・サポートの働きというものをどのように切り出そうとしているのかが鮮明に見えてくる。
まず、本書においてピア・サポートは、(情報交換の場というよりも)誰かが自らの物語を語り、他者がそれを聴く場として性格づけられる。
しかし、それはただ漠然と〈語る-聴く〉という関係が成立していればいいというわけではない。ピア・サポートが有効に働くのは、そこにある〈語る-聴く〉関係が、ある特質を備えた〈語る-聴く〉関係だからである。その特質とはすなわち、別様な語りの可能性をくみ上げることができる、という特質にほかならない。
それは、支配的な物語に語りが脅かされない空間をつくることによって初めて実現されるものである。つまり第一には、共同体の物語によって社会の支配的な物語を相対化することによって。第二には、未だ語られていないものに耳を澄ます姿勢を通して、共同体の物語の固定化を防ぐことによって。
こうして実現された特殊な〈語る-聴く〉関係こそが、ピア・サポートの場の中で、自己物語探しのプロセスを歩む自由を人に担保する。他者の語りに刺激されながら、しかし誰にも紋切り型の物語を押し付けられることなく、言葉を探し、言葉をつなぎ、自己の経験と感情に、物語の中での居場所を与えていく。何かを正解とみなす必要はなく、別様な語り方が常にあっていい。そうやって行ったり来たりを繰り返しているうちに、現在の自分の肌になじむ肯定的な物語の形が、ある時パッと見えてくる。そんなプロセスだ。その物語が、その人の過去や現在に新しく意味を与え、そして未来の方向を示すのである。
このように、本書はピア・サポートを、別様な語りの可能性をくみ上げることによって人を支える場として描き出しているのだと言える。物語探しのプロセスを歩むのは苦しみを抱えたその人自身だが、そのプロセスを自由に歩めるかどうかは、その語りを受け止める空間がいかなるものであるか、聴き手がいかなる聴き手であるかにかかっている。良きピア・サポートは、別様な語りの可能性をくみ上げるためのしくみと、それに耳を澄ますことのできる聴き手によって成り立つのだ。
5.良き聴き手であるとはどういうことか
結びに入ろう。この本が刺激的なのは、ピア・サポートやナラティヴ・アプローチという個別的な関心を超えて、この本の全体が、「聴く」ということについて私たちに問いかけてくるからである。良き聴き手であるとはどういうことであろうか、と。
思うに、本書が示すその答えは次のようなものであろう。すなわち、良き聴き手であるとは別様な語りの可能性に敏感であり続けるということ、そしてそのために、未だ語られていないものに常に耳を澄ますということである、と。
聴き手とは、ただ語りを受動的に受け止めるだけの存在ではない。
なぜなら聴き手には、自覚的にであれ無自覚的にであれ、物語の語り手を導く目に見えない力があるからだ。聴き手の応答のあり方は語り手の語り方のガイドとなる。また、ピア・サポートにおいてそうであるように、聴き手自身が自らの物語を語ることが、語り手にヒントを与えることもあるだろう。そんな時、その聴き手がもしも紋切り型の支配的な物語にとらわれていたなら、語り手の語りもまた、紋切り型の中に閉じ込められてしまうことになる。
したがって、良き聴き手は、紋切り型の物語とは別様な物語の形があっていいんだということを感覚的に知っていなくてはならない。そして、別様な新しい物語が実際に立ち現れるに至るためには、聴き手が、語り手の「声」の内に示された未だ言葉にならぬものに耳を澄まし、それをかき消さないようにしなくてはならない。人が自らの物語を編み直そうとする時、そこには、こうした意味で良き聴き手となることのできる他者がいなくてはならないのである。
ピア・サポートに限らず、聴くという営みは、私たちの生活の中でありふれた営みである。言葉によるコミュニケーションがあるところには、すべて「聴く」という営みが微細に存在している。自ら言葉を紡ぐ時ですらも、自分自身の「声」に耳を傾けるという意味では、「聴く」という行為がそこにある。だが私たちは常に良き聴き手であれるわけではない。私たちはそれほど強くはないし、それほど自由な存在でもない。本書『ピア・サポートの社会学』は、そんな中で、良き聴き手であろうと欲する者を支えてくれる一冊である。それは本書が、まさしく「聴き手」たちの「物語」を私たちに提示するからである。
そして最後に言っておきたいのは、その物語を提示しているのは本書で語られる内容だけではないということだ。その内容を語る著者たちの姿勢そのものにもまた、その物語が示されている。その姿勢とはまさに、ピア・サポートを単純な図式に押し込めて語ることをせず、別様な語りを探し続けようとする姿勢である。彼ら自身が良き聴き手であろうとしているからこそ本書ができあがったのであり、本書に良き聴き手であることを私たちに促す力がある一番の理由は、そこにあるのかもしれない。
[引用文献]
*1:英語の"narrative"と"story"、日本語の「物語」と「語り」、これら4つの語の関係はナラティヴ・アプローチを語る際に非常によく話題にされることであるが、本記事はナラティヴ・アプローチの説明をすることが主目的ではないため、ここに深入りすることは避けたい。
*2:ただし、本書は物語を〈事象の連鎖〉とは定義しても、〈事象の連鎖を語る言語形式〉とは定義していない。このことは、本書において、物語は直接的な言葉ばかりでなく「声」や「身体」によっても示されるとされていることと関係するかもしれない。もしそうだとすれば、この定義の差異は重要な差異だと言える。
*3:ナラティヴ・セラピーの提唱者の一人であるホワイトは次のように述べている。「幾度も治療を必要とするような問題を人々が抱えるのは、彼らが自らの経験を「物語る」("storying")際の物語が、あるいは彼らの経験が他者によって「物語られる」("storied")際の物語が、彼らの生きられた経験(lived experience)を十分に表現していないときである」(White, M. & Epston, D. , Narrative Means to Therapeutic Ends, p14)
*4:野口は次のように述べている。「簡単につくり変えられるのであれば、なにもナラティヴなどという概念を持ち出してきて、難しい説明をする必要はない。それがきわめて困難であること、簡単には変更できないからこそ、逆にわたしたちは、「ナラティヴ」という存在の重さに注目せざるを得ないのである」(野口裕二『物語としてのケア』p58)
*5:その6つの着眼点というのは、「筋(プロット)」「登場人物の性格づけ(キャラクター)」「モチーフ」「テーマ(主題)」「声」「身体」の6つである。本記事本文では触れられないが、最後の「身体」に着目するという点も本書の特徴的な部分だと言える。